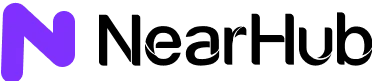テレワークやオンライン会議が広がる中、画面共有アプリは業務効率化に不可欠なツールとなっています。本記事では、50以上のアプリを比較し、用途別におすすめの5つの画面共有アプリ(Zoom、Slack、Google Meet、Surfly、CoScreen)及びそれぞれの強みや注意点、最適な利用シーンを解説しています。また、単なる画面共有にとどまらず、双方向のコラボレーションを可能にするNearHub Board S55にも注目しています。
1.画面共有を成功させるために、ベストなアプリを使おう
うまく活用すれば、画面共有はリモートでのドキュメント共同編集、ウェブブラウジング、製品デモ、新規顧客のオンボーディングなどをスムーズに実現できます。しかし、うまくいかなければ「画面見えてますか?」の悪夢が何度もよみがえり、フラストレーションの元になります。
だからこそ、最適な画面共有アプリを選ぶことはとても重要です。私はリモートワーク歴10年の中で、チームやクライアントとの連携にさまざまな画面共有ツールを使ってきました。本記事は数年かけてアップデートを重ねており、その中で得た「使いやすいツール」「困った点」「二度と使いたくない機能」なども含めてご紹介します。
2025年版では、50種類以上のアプリを調査し、実際に操作性やパフォーマンスを比較検証します。そこから厳選した、用途別におすすめの画面共有ツール5選を紹介します。
2.専用の画面共有アプリ、本当に必要?
本題に入る前に、自分にとって「専用の画面共有アプリ」が本当に必要かを考えてみてください。
近年、多くのアプリに「おまけ機能」として画面共有が搭載されるようになっています。特に、以下のようなツールには標準で画面共有機能があることが多いです。
- オンラインホワイトボード(例:Miro)
- マインドマップアプリ
- フローチャート・ダイアグラム作成ツール
- ワイヤーフレーム作成ツール
- 新人研修や社員オンボーディングソフト
- カスタマーサポート・リモート接続支援ツール
- ライブチャットアプリ(ユーザー画面を見ながら案内可能)
- ウェビナー・オンラインセミナー向けソフト
- 顧客対応に特化した動画通話プラットフォーム(例:24sessions)
- セールス支援ツール(例:Demodesk、ClearSlide)
つまり、普段使っているツールにすでに画面共有が組み込まれている可能性が高いのです。特別なニーズがなければ、あえて専用アプリを導入する必要はないかもしれません。
とはいえ、高度なコントロールや安定性、同時参加者数、共同編集などの点で優れた体験を求めるなら、やはり専用アプリの方がベターです。
3.「良い画面共有アプリ」の条件とは?
画面共有は単に「画面を見せる」だけでなく、社内会議、プレゼン、セールスデモ、設計レビューなど多様な目的に使われます。今回の選定基準は以下の通り:
- 簡単にアクセスできること:ブラウザから使え、アプリのインストール不要なものが理想。
- 共同作業に強いこと:注釈、共同編集、ホスト交代、共同ブラウジングなど。
- モバイルでも快適に使えること:スマホやタブレットでもストレスなく共有可能か。
- 他ツールとの連携:録画保存、スケジューリングなどの自動化。
- 価格が現実的であること:無料プランが充実しているか、費用対効果が高いか。
- 画面の細かい共有設定:どのウィンドウを誰に見せるかを柔軟にコントロール可能か。
なお、TeamViewer や Quick Assist のような「リモートアクセス特化型ソフト」は除外しています。今回ご紹介するのは、あくまで「社内会議やコラボレーションに適した画面共有ツール」です。
4.用途別|2025年おすすめの画面共有アプリ
4.1 普段使いに最適:Zoom

対応:Web、Windows、Mac、Linux、iOS、Android
メリット:
- 知名度抜群、多くの人がすでに使っている
- 無料プランでも十分高機能
- 画面共有コントロールが非常に豊富、pc 画面共有リアルタイム可能
デメリット:
- ブラウザ版では画面共有の細かい制御がやや制限される
Zoom はチームの社内会議やプレゼン、ウェビナーに最適な定番ツールです。回線が不安定でも帯域に合わせて画質を自動調整してくれるため、Zoom 画面共有中も安心して使えます。無料プランでも100人まで同時接続可能で、機能も充実します。画面の一部だけを共有したり、iPad画面をAirPlay経由で映したりすることも可能です。
4.2 社内ミーティング向け:Slack

対応:Web、Windows、Mac、Linux、iOS、Android
メリット:
- 無料プランでも画面共有可能、pc 画面共有リアルタイム可能
- 「ハドルミーティング」で気軽に会話・共有できる
デメリット:
- 参加者はワークスペースメンバーに限られる
- 画面の一部だけ共有することはできない
Slackを普段使っている企業であれば、画面共有もそのままSlack内で完結できます。Slackアプリ連携で、チャネル上で共有されたファイルや会話はすべて記録され、あとで検索も可能です。さらに、複数人で画面に注釈をつけたり、マウスカーソルを同時に動かしたりと、協働作業に強いのが魅力です。
4.3 Googleユーザーに最適:Google Meet

対応:Web、iOS、Android
メリット:
- Gmailから即座に開始可能、pc 画面共有リアルタイム可能
- GoogleカレンダーやDriveとの連携がシームレス
デメリット:
- 画面の一部だけを共有することは不可
Google Meetは、GmailやGoogleカレンダーと統合されているので、日常的にGoogleを使っている人には非常に便利です。スマホからでも直感的に画面共有やgoogle meet資料共有でき、ホワイトボード機能(Jamboard)も活用可能です。
4.4 顧客サポート・セールスに最適:Surfly

対応:Web
メリット:
- クリック一つでセッション参加可能
- 顧客と「同じ画面」を見ることに特化
デメリット:
- 無料プランなし・価格は高め
- 画面の一部だけの共有はできない
Surflyは、セールスやカスタマーサポートに特化した「共同ブラウジング」ツールです。ユーザー側にソフトをインストールしてもらう必要がなく、ワンクリックでサポートが開始可能です。担当者がユーザーのブラウザ内で直接アシストできます。
4.5 開発チーム向け:CoScreen

対応:Mac、Windows(Linuxは一部対応)
メリット:
- 複数人で同時に画面共有・操作可能
- アプリごとに直感的に画面を共有できる
デメリット:
- 参加者も全員アプリをダウンロードする必要あり
- 画面の一部だけの共有は不可
CoScreenはエンジニア、プロダクト開発チーム向けに設計された画面共有アプリです。複数メンバーが同時にアプリを操作できるため、ペアプログラミングやコードレビューに最適です。ビジュアル的にもわかりやすく、チーム全体でリアルタイムに作業を進められます。
5.「見る」から「共に創る」へ——NearHub Board S55スマートボードが再定義する画面共有の未来
テレワークやハイブリッドワークの普及により、「画面共有アプリ」は現代のビジネスや教育現場に欠かせない存在となりました。NearHub Board S55は、その「画面共有」の在り方を根本から進化させ、次世代のオールインワン・スマートディスプレイです。4K高精細タッチパネル、内蔵PC、マイク、AIカメラを備え、ZoomやTeamsでの社内会議をケーブルレスで即座に開始可能。さらに、複数人で同時に書き込める電子ホワイトボード、ワイヤレス画面共有、リアルタイム共同編集といった機能により、従来の画面共有できるアプリでは実現しづらかった「双方向のコラボレーション」を実現します。
「ただの画面共有」ではなく、参加者全員がアイデアを出し合い、ホワイトボードに書き込み、資料を直接操作できる。NearHubは、まさに「画面共有と共同作業が一体化した新しい体験」を提供するツールです。
教育現場では生徒の理解度を高め、オフィスでは社内会議の生産性を向上させます。実際に導入した企業や教育機関からは「画面共有のストレスがなくなった」「遠隔会議でもその場で話し合っているように感じる」といった声が寄せられています。また、NearHubは55型、65型、75型など、さまざまなサイズをご用意しており、すべて買い切り型にてご提供しています。全国送料無料、初期設定サポート付きで、届いたその日からすぐに使えます。
「見る」だけの画面共有から、「一緒に作る」画面共有へ。NearHubで、次世代のコミュニケーションを始めてみませんか?
6.結局どれを選べばいいの?
用途によって、必要な機能は大きく変わります。「注釈機能が欲しいのか」「アプリインストールが不要なものが良いのか」「社内限定か、外部との連携も必要か」など、自分のニーズを明確にして選ぶのがベストです。
今回紹介した5つの画面共有アプリは、それぞれが異なる強みを持っています。自分のチームやクライアントとの連携スタイルに合ったものを選んで、ストレスのない画面共有体験を実現しましょう!