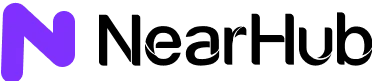近年、イヤホン市場で急速に存在感を増している「開放型イヤホン」。周囲の音を聞きながら音楽を楽しめるという、従来のイヤホンとは一線を画す体験が多くのユーザーに支持されています。
特に「ワイヤレスイヤホン開放型」モデルの進化は目覚ましく、ランニングやウォーキングなどのスポーツシーンはもちろん、オフィスワークや家事、育児といった日常生活にもシームレスに溶け込むアイテムとして注目を集めています。
しかし、「開放型イヤホンって何?」「音漏れは?」「どんなモデルを選べばいい?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、開放型イヤホンの基礎知識から、メリット・デメリット、そして2025年最新のおすすめモデルの選び方まで、徹底的に解説します。あなたのライフスタイルに最適な一台を見つけるための、完全ガイドです。
そもそも「開放型イヤホン」とは? 密閉型との違い
「イヤホン開放型」と聞いても、ピンとこないかもしれません。まずは、イヤホンの基本的な2つのタイプ、「開放型(オープンイヤー)」と「密閉型(クローズド)」の違いから理解を深めましょう。
密閉型(クローズド型)イヤホンとは
私たちが一般的に「イヤホン」と聞いて想像するものの多くは「密閉型」です。
代表的なのは、耳栓のように耳の穴(外耳道)に深く差し込むタイプの「カナル型イヤホン」です。このタイプは、イヤホンの先端にあるイヤーピースで耳の穴を物理的に塞ぎます。
- メリット:
- 高い遮音性: 耳を塞ぐため、周囲の騒音(電車の走行音、カフェの話し声など)を大幅にカットできます。
- 音漏れの少なさ: 音が外に漏れにくいため、公共の場でも安心して使用できます。
- 迫力のある低音: 音が鼓膜に直接届きやすく、密度のある力強い低音(バス)を感じやすいのが特徴です。
- デメリット:
- 圧迫感と疲労: 長時間装着していると、耳の穴に圧迫感を感じたり、痛みが出たりすることがあります。
- 周囲の音が聞こえない: 遮音性が高い反面、車や自転車の接近、人からの呼びかけに気づきにくいという安全上の懸念があります。
- 閉塞感: 自分の声がこもって聞こえる「閉塞感」が苦手という人も少なくありません。
開放型(オープンイヤー型)イヤホンとは
一方、「開放型イヤホン」は、その名の通り耳を完全に塞がない構造をしています。ドライバーユニット(音を出す部分)の背面に意図的に開口部を設けたり、耳の穴の手前にスピーカーを配置したりすることで、空気が自由に動けるように設計されています。
- メリット:
- 周囲の音が聞こえる(環境音の取り込み): これが最大の利点です。音楽を聴きながらでも、周囲の環境音(車の音、インターホン、同僚の声)を自然に聞き取ることができます。
- 圧迫感のない快適な装着感: 耳の穴を塞がないため、長時間の使用でも疲れにくく、圧迫感や閉塞感がほとんどありません。
- 自然で広がりのある音場: 音が耳の周りの空間で自然に響くため、スピーカーで聴いているような、広がりと抜け感のあるサウンド(音場)を楽しめます。
- デメリット:
- 音漏れのしやすさ: 構造上、音が外に漏れやすい傾向があります。静かな図書館や満員電車での大音量使用には注意が必要です。
- 遮音性の低さ: 周囲の音が聞こえることの裏返しで、騒がしい場所では音楽が聞こえにくくなることがあります。
- 低音の迫力: 密閉型に比べると、重低音の「圧」は感じにくい場合があります。(ただし、近年の技術進化でこの点は大幅に改善されています)
なぜ今「開放型イヤホン」が選ばれるのか? メリットを深掘り
開放型イヤホンの基本がわかったところで、なぜ今これほどまでに「開放型ワイヤレスイヤホン」が注目されているのか、その具体的なメリットを日常生活のシーンと合わせて深掘りします。
1. 圧倒的な安全性と利便性(ながら聴き)
開放型イヤホンの最大の強みは「ながら聴き」にあります。
- スポーツシーン: ランニングやサイクリング中、背後から迫る車や自転車、他のランナーの気配を察知できます。安全を確保しながら、お気に入りの音楽でモチベーションを上げることが可能です。
- オフィスワーク: 音楽やポッドキャストを聴きながらでも、同僚からの呼びかけや電話の着信音を聞き逃しません。リモートワーク中のインターホンや家族の声にも対応できます。
- 家事・育児: 料理中や掃除中、火の様子や子供の呼びかけに気づくことができます。音楽で気分を上げつつ、家庭内のコミュニケーションも疎かにしません。
2. 耳への負担を最小限に抑える快適な装着感
「カナル型イヤホン」が苦手な人の多くは、あの独特の「圧迫感」や「異物感」を理由に挙げます。開放型イヤホンは、この問題を根本から解決します。
耳の穴を塞がないため、耳内部の湿度が上がりにくく、蒸れやかゆみを防ぎます。特に、外耳炎になりやすい人や、長時間のWEB会議でイヤホンをつけっぱなしにする必要がある人にとって、開放型は救世主とも言える選択肢です。
3. まるでBGM。自然で疲れないサウンド体験
密閉型イヤホンで音楽に「没入」するのも素晴らしい体験ですが、時にはそれが「聴き疲れ」の原因にもなります。
開放型イヤホンが提供するのは、まるで空間にBGMが流れているかのような、非常に自然なサウンドです。音楽が頭の中で鳴っているのではなく、自分の周囲で鳴っているように感じられるため、リラックスしながら長時間音楽を楽しむことができます。この「抜けの良い音」は、アコースティックな音楽や、ライブ音源、ポッドキャストなどとの相性が抜群です。
開放型イヤホンのデメリットと注意点
もちろん、開放型イヤホンにも弱点はあります。購入後に「失敗した」とならないよう、デメリットもしっかりと把握しておきましょう。
1. 音漏れのリスク
最も注意すべき点が「音漏れ」です。耳を塞がない構造上、音が外にも拡散しやすくなります。
最近の高性能モデルでは、音の指向性をコントロールし、音漏れを最小限に抑える技術(逆位相の音を当てて打ち消すなど)が採用されていますが、ゼロではありません。
静かなオフィスや図書館、満員電車など、周囲との距離が近く静かな環境では、音量を控えめにする配慮が必要です。
2. 騒音下でのリスニング
遮音性がないため、電車の走行音、工事の騒音、強風の音などが激しい場所では、音楽の細部がかき消されてしまうことがあります。
もし、通勤・通学の電車内など、騒がしい場所での利用がメインで、音楽への没入感を最優先したい場合は、ノイズキャンセリング機能付きの密閉型イヤホンの方が適しているかもしれません。
開放型イヤホンは、「周囲の音も聞きながら音楽も楽しみたい」というニーズに最適化された製品であることを理解しておくことが重要です。
開放型イヤホンの主な種類と特徴
「開放型イヤホン」と一口に言っても、その形状や音の出し方にはいくつかの種類があります。あなたの使い方に合ったタイプを選びましょう。
1. 耳を塞がない「オープンイヤー型」(空気伝導・骨伝導)
現在、「開放型ワイヤレスイヤホン」の主流となっているのが、耳の穴を完全に塞がず、耳の近くにスピーカーを配置するタイプです。これらは広義の「オープンイヤー 型イヤホン」と呼ばれます。
- 空気伝導(エアコンダクション):
- 耳の穴の近くに小型スピーカーを配置し、そこから出た音を「空気の振動」として鼓膜に届けます。
- 私たちが普段聞いている音と同じ仕組みであるため、音質が非常に自然で、高音域のクリアさや音の広がりに優れています。
- 「骨伝導は音がこもって聞こえるのが苦手」という人にもおすすめです。
- 骨伝導(ボーンコンダクション):
- こめかみや耳の軟骨部分に振動子(バイブレーター)を当て、その「骨の振動」によって音(蝸牛)に直接音を届けます。
- 耳の穴を完全にオープンにできるため、環境音の聞き取りやすさは抜群です。
- ただし、構造上、高音域の再現性や音の解像度は空気伝導に一歩譲る場合があり、振動がくすぐったいと感じる人もいます。
2. 安定感抜群の「耳かけ型」
スポーツシーンでの利用を強く意識しているのが、「耳にかけるイヤホン」です。
耳全体を覆うようにフックをかけることで、激しい動きでもイヤホンがズレたり落下したりするのを防ぎます。上記のオープンイヤー型とこの耳かけ(イヤーフック)デザインを組み合わせたモデルが、現在のスポーツ用開放型イヤホンのトレンドとなっています。
眼鏡やマスクとの相性も考慮する必要はありますが、装着の安定感を最重要視する人には最適な形状です。
3. 従来型の「インナーイヤー型」
耳の穴の入り口に軽く引っ掛けるようにして装着する、昔ながらのタイプです。Appleの初期のAirPods(Proではないモデル)がこの代表例です。
耳の穴を完全に塞ぎませんが、カナル型ほどではないものの、ある程度の密閉感はあります。装着感が軽く、開放型と密閉型の中間的な存在と言えます。ただし、耳の形によってはフィットしにくく、外れやすいという欠点もあります。
【必見】開放型イヤホン おすすめモデルの選び方
ここからは、数ある「bluetooth イヤホン 開放 型」モデルの中から、自分に合った一台を選ぶための具体的なチェックポイントを解説します。
H3: 1. 接続方式:主流は「ワイヤレスイヤホン開放型」
現在、開放型イヤホンの新製品のほとんどはワイヤレス(Bluetooth)モデルです。ケーブルの煩わしさから解放され、スポーツや家事との相性が抜群です。
選ぶ際は「Bluetoothのバージョン」に注目しましょう。Bluetooth 5.0以上(現在は5.2や5.3が主流)に対応しているモデルは、接続の安定性、低遅延、省電力性能に優れています。
H3: 2. 装着感と形状:自分の利用シーンに合わせる
前述の「種類」とも重複しますが、装着感は最も重要な要素です。
- スポーツ・運動がメイン: 汗や雨に強く、安定感のある「耳かけ型」が最適です。
- 長時間のリモートワークやリラックス: 圧迫感のない「オープンイヤー型」がおすすめです。眼鏡をかけている人は、テンプル(つる)と干渉しないか、可能であれば試着してみると良いでしょう。
- 音質と装着感のバランス: 自然な音質を求めるなら「空気伝導」タイプ、環境音の聞き取りやすさを極限まで求めるなら「骨伝導」タイプを検討します。
H3: 3. 音質:対応コーデックとドライバー
音質にこだわるなら「対応コーデック」をチェックしましょう。コーデックとは、Bluetoothで音声を伝送する際の「圧縮方式」のことです。
- SBC: 標準的なコーデック。音質はそこそこですが、ほぼ全ての機器で使えます。
- AAC: iPhoneやiPadなど、Apple製品で主に使用されます。SBCよりも高音質・低遅延です。
- aptX (アプトエックス): Androidスマートフォンで多く採用されています。AACと同等以上に高音質で、特に遅延が少ないのが特徴です。動画視聴やゲームにも適しています。
「開放型イヤホン」は構造上、低音が抜けやすい傾向がありましたが、最近のモデルは「大口径ドライバー」を搭載することで、その弱点を克服しています。ドライバーサイズ(例:16mmなど)が大きいほど、豊かで迫力のある低音を鳴らしやすい傾向があります。
H4: 4. 防水性能:IPX等級を確認しよう
汗をかくランニングや、急な雨が心配な屋外での使用、あるいはお風呂場でのリラックスタイムに使いたい場合は、「防水性能」が必須です。
防水性能は「IPX〇」という等級で示されます。
- IPX4: 「防沫形」。汗や小雨程度なら問題ないレベル。一般的なスポーツモデルはこの等級です。
- IPX5: 「防噴流形」。シャワーなどの水流を浴びても大丈夫なレベル。
- IPX7: 「防浸形」。一時的に水中に沈めても浸水しないレベル。
自分の使用シーンに合わせて、最低でもIPX4以上を選ぶと安心です。
H5: 5. バッテリー持続時間と急速充電
ワイヤレスモデルである以上、バッテリー性能は重要です。
- イヤホン本体の連続再生時間: 一度の充電で何時間再生できるか。
- 充電ケース込みの総再生時間: ケースで何回フル充電できるか。
通勤・通学で毎日使うなら、イヤホン本体で6〜8時間、ケース込みで24時間以上あると安心です。また、「10分の充電で1時間再生」といった「急速充電」機能があると、うっかり充電を忘れた時にも便利です。
特におすすめの「開放型ワイヤレスイヤホン」モデル紹介
数々の選び方を紹介してきましたが、ここでは特に注目すべき、快適さと高音質、そして利便性を両立したおすすめのモデルをご紹介します。
Nearity MemPod Fit 2:リモートワークからランニングまで。日常に溶け込む高性能モデル
「カナル型の圧迫感が苦手だけど、音質も妥協したくない」「WEB会議で途切れない安定性が欲しい」「運動中も使いたい」…そんな多様なニーズに応えるのが、Nearityの最新空気伝導モデル「Nearity MemPod Fit 2」です。この耳掛けワイヤレスイヤホンが実際の生活シーンでどのように活躍するのか、具体的に見ていきましょう。
シーン1:ハイブリッドワークとWEB会議
リモートワーク中、PCでのWEB会議に集中していると、個人のスマートフォンに着信が。そんな時も「Nearity MemPod Fit 2」なら慌てる必要はありません。便利なマルチポイント機能でPCとスマホに同時接続しており、イヤホンを操作するだけでシームレスに通話へ切り替えられます。
さらに、PCのBluetooth接続が不安定になりがちなカフェや、電波が混線するオフィスでも安心です。付属の専用USBドングルを使えば、PC内蔵のBluetoothをバイパスし、非常に安定した低遅延接続を確立します。会議の声が途切れるストレスから解放され、自分の声もこもらず自然に話せるので、長時間の議論も快適です。
シーン2:ランニングやフィットネス
週末のランニング。安全のために周囲の音は聞きたいけれど、音楽の迫力も欲しい。「Nearity MemPod Fit 2」は、人間工学に基づいた「耳にかける イヤホン」デザインを採用。激しく動いてもズレにくく、耳にそっと乗せるような軽い装着感で、長時間の運動でも快適です。IPX5の防水性能で、突然の雨や大量の汗も問題ありません。
シーン3:家事やリラックスタイム
音楽を聴きながら料理や掃除。大口径(16.2mm)ドライバーが奏でる豊かな低音とクリアなボーカルが、いつもの家事を少し楽しくしてくれます。それでいて、玄関のインターホンや家族の呼びかけは聞き逃しません。独自の音漏れ防止技術により、家族が寝静まった夜にポッドキャストを聴く際も、音量を上げすぎなければ隣で眠る家族の妨げになりにくい設計です。
このように、「Nearity MemPod Fit 2」耳掛けワイヤレスイヤホンは、「ながら聴き」の安全性・利便性と、ピュアな音楽体験、さらにビジネスユースの安定性まで高いレベルで融合させた、あらゆる日常シーンに寄り添う「開放型ワイヤレスイヤホン」です。

開放型Bluetoothイヤホンの便利な機能と周辺知識
最新の「bluetooth イヤホン 開放 型」モデルには、日々の使い勝手を格段に向上させる便利な機能が搭載されています。また、接続に関する少しマニアックな知識も知っておくと役立ちます。
1. マルチポイント接続:2台同時接続の活用法
「マルチポイント」とは、1台のイヤホンを、スマートフォンとPC、あるいは2台のスマートフォンなど、2台のデバイスに同時にBluetooth接続できる機能です。
例えば、会社のPCでWEB会議をしながら、個人のスマートフォンに着信があった場合、イヤホンが自動でスマートフォンに切り替わり、そのまま通話に出ることができます。通話が終われば、自動でPCの音声に戻ります。
この機能があるだけで、デバイス間の接続をいちいち切り替える手間がなくなり、作業効率が劇的に向上します。この便利な機能の詳しい設定や活用法については、「bluetoothイヤホン 2台同時接続方法」のガイドで詳しく解説しています。先ほどご紹介した「Nearity MemPod Fit 2」も、この便利なマルチポイント機能に対応しています。
2. ドングルとは? PC接続を安定させる秘密兵器
「ドングルとは?」と疑問に思う方もいるでしょう。 「ドングル(Dongle)」とは、PCなどのUSBポートに差し込んで機能を追加するための小型の機器を指します。Bluetoothイヤホンの文脈では、主に「Bluetooth USBアダプタ(トランスミッター)」を意味します。
なぜドングルが必要なのか?
多くのノートPCには標準でBluetoothが内蔵されていますが、以下のような問題が発生することがあります。
- Bluetoothのバージョンが古く、接続が不安定。
- OSのドライバとの相性が悪く、音が途切れたり、マイクが認識されなかったりする。
- 特にWEB会議中、音声(HFPプロファイル)と音楽(A2DPプロファイル)の切り替えがうまくいかない。
こんな時、PC内蔵のBluetoothをオフにし、専用の「ドングル」をUSBポートに挿すことで、問題が解決することが多々あります。
ドングルは、それ自体がBluetoothの親機として機能し、イヤホンと1対1で安定した通信チャネルを確立します。特に、低遅延コーデック(aptX LLなど)に対応したドングルを使えば、PCでの動画視聴やゲームの音ズレを最小限に抑えることも可能です。
もし「開放型ワイヤレスイヤホン」をPCで使っていて接続トラブルに悩んでいるなら、「ドングル」の導入は非常に有効な解決策となります。なお、「Nearity MemPod Fit 2」のように、製品にあらかじめ専用のドングルが付属しているモデルもあり、購入後すぐに安定したPC接続が期待できるため特におすすめです。
まとめ:あなたの生活に「開放型イヤホン」を取り入れよう
今回の記事では、「開放型イヤホン」の魅力と選び方について、基礎知識から応用テクニックまで詳しく解説してきました。
開放型イヤホンのポイント:
- 最大の魅力は「ながら聴き」: 周囲の音を聞き取れるため、安全性が高く、コミュニケーションを妨げません。
- 圧倒的な快適さ: 耳を塞がないため、圧迫感や蒸れがなく、長時間の使用に最適です。
- 音質は進化している: 従来の「音が軽い」イメージは過去のもの。大口径ドライバー搭載モデルなら、迫力あるサウンドも楽しめます。
- 利用シーンで選ぶ: スポーツなら「耳かけ型」、音質と快適さなら「空気伝導オープンイヤー型」など、形状の選択が重要です。
- 便利機能をチェック: 「マルチポイント」や「専用ドングル」、「防水性能」は、使い勝手を大きく左右します。
「イヤホンは音楽に没入するためだけのもの」という時代は終わりつつあります。開放型イヤホンは、音楽を私たちの日常生活の「BGM」としてシームレスに溶け込ませ、生活の質(QOL)そのものを向上させてくれるデバイスです。
圧迫感から解放された快適なリスニング体験と、WEB会議などでの安定した接続を求めているなら、ぜひNearity MemPod Fit 2のような、最新技術が詰まった「開放型ワイヤレスイヤホン」をチェックしてみてください。あなたのオーディオライフが、より安全で、より快適なものに変わるはずです。
「開放型イヤホン」に関するよくある質問 (FAQ)
Q1: 開放型イヤホンと密閉型イヤホンの最大の違いは何ですか?
A1: 最大の違いは「耳を塞ぐかどうか」です。密閉型(カナル型など)は耳の穴を塞いで遮音性を高めるのに対し、開放型は耳を塞がず、周囲の音も聞こえるように設計されています。これにより、開放型は圧迫感がなく快適ですが、音漏れはしやすく、遮音性は低くなります。
Q2: 開放型イヤホンは音漏れがひどいですか?
A2: 従来のモデルや安価なモデルでは音漏れが目立つものもありますが、最近の「開放型ワイヤレスイヤホン」は技術が大きく進歩しています。音の指向性をコントロールしたり、逆位相の音を出して音漏れを打ち消す技術を採用したりすることで、実用上問題ないレベルまで音漏れを抑えたモデル(例:Nearity MemPod Fit 2)が増えています。ただし、密閉型に比べれば漏れやすいため、静かな場所では音量に配慮するのがマナーです。
Q3: ランニングやスポーツにおすすめの開放型イヤホンは?
A3: スポーツ用途では、「装着の安定性」と「防水性能」が重要です。激しい動きでも外れにくい「耳にかけるイヤホン」のデザインを採用したモデルを選びましょう。また、汗や雨に耐えられるよう、防水性能はIPX4以上(できればIPX5)あると安心です。
Q4: 「ドングル」を使うメリットは何ですか?
A4: PCで「bluetooth イヤホン 開放 型」モデルを使う際に、接続を安定させることが最大のメリットです。PC内蔵のBluetoothは、バージョンが古かったり、他の電波と干渉したりして不安定になることがあります。「ドングル と は」PCのUSBポートに挿す専用のBluetoothアダプタのことで、これを使うとイヤホンと1対1の強力な接続が確立され、音途切れや遅延、マイクの不具合などを解消できる場合があります。「Nearity MemPod Fit 2」のように、最初から製品に専用ドングルが付属しているモデルは、PCでの利用に最適です。
Q5: 開放型ワイヤレスイヤホンはWEB会議に使えますか?
A5: 非常に適しています。開放型イヤホンは耳を塞がないため、自分の声がこもらず、自然な感覚で会話ができます。また、長時間の会議でも耳が疲れにくいという大きなメリットがあります。PCとスマホに同時接続できる「マルチポイント」機能搭載モデル(例:Nearity MemPod Fit 2)を選べば、PCでの会議中にスマホの着信にもシームレスに対応でき、さらに便利です。